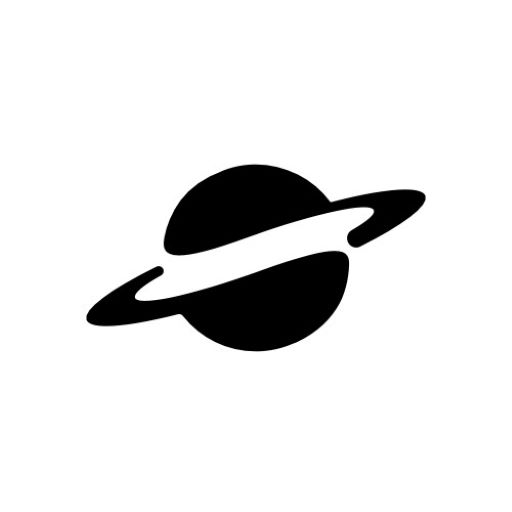1.不確かさ
1.1不確かさとは?
実験において物理量を測定したとき、一回測定しただけで実験が終わることはない。ただ一回の測定では、その値がなんらかの理由で偶然その値になった可能性があるからである。複数回測定をしてその値の妥当性を見たいのだ。そこで物理実験系で用いられるのが不確かさと呼ばれるものである。
$$ \text{測定結果 = データの平均} \pm \text{不確かさ 単位} $$
不確かさによって、データが信用できる範囲を見ることができるのである。文字だとわかりづらいので実際のデータの例を見てみよう。
| 測定回数 | 長さ [cm] |
|---|---|
| 1回目 | 10.2 |
| 2回目 | 10.3 |
| 3回目 | 10.1 |
| 4回目 | 10.4 |
| 5回目 | 10.2 |
このような計測結果だった場合、以下のように結果を表示する。
$$ L~=~10.24\pm0.05~\mathrm{cm} $$
1.2不確かさの計算法
詳しい理論は置いといて、計算方法を習得しよう。計測結果が次の場合を考えよう。
| 測定回数 | \( X[\text{unit}] \) |
|---|---|
| 1回目 | \( x_1 \) |
| 2回目 | \( x_2 \) |
| \( \vdots \) | \( \vdots \) |
| \( n \)回目 | \( x_n \) |
| \( \vdots \) | \( \vdots \) |
| \( N \)回目 | \( x_N \) |
データの平均は、相加平均を採用して、
$$ \bar{X}=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^N x_n $$
不確かさは、
$$\sigma_{\bar{X}}=\sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{n=1}^{N}\left( x_n-\bar{X}\right)^2 }$$
これらを用いて表現すると、
$$X~=~\bar{X}\pm k\sigma_{\bar{X}}~\mathrm{unit}$$
ここで、\(\mathrm{unit}\)は、任意の単位を意味する。また、\(k\)は、包含係数という。この包含係数によって値の信用が変わり、真の値が表現された範囲である確率がわかる。(\(k=1\text{の時:約}68.3\%\),\(~~~k=2\text{の時:約}95.4\%\),\(~~~k=3\text{の時:約}99.74\%\))
1.3不確かさの有効数字
平均と不確かさが計算されたとき、どの値までを有効数字として、記述するかが大事になってくる。まず、不確かさの桁数で着目するのは、1桁~2桁である。以下の例を見ておく。
\[0.006324\Rightarrow 0.006\] \[0.002355\Rightarrow 0.0023\] \[0.00356324\Rightarrow 0.0036\] \[0.00396324\Rightarrow 0.0040\] \[0.00456324\Rightarrow 0.005\]どの場合にも適用されるのが、四捨五入をすること。一番最初に出てくる数に着目して、その数が4以上だったら、不確かさは、1桁だけとる。一番最初に出てくる数に着目して、その数が3以下だったら2桁とる。この三つのルールにしたがって有効数字を定める。 そこから、平均の有効数字は、不確かさと同じ位まで表示する。いくつか例を示しておく。
ここでは、包含係数を1としている。 実際に、自分で計算してみると、理解が深まるかもしれない。
2.合成不確かさ
2.1合成不確かさとは?
例えば、こんな状況を考える。
このときの電流の不確かさは、単に不確かさの割り算ではない。次のようになる。
\[I=544\pm8 ~\mathrm{C/s}\]2.2合成不確かさの計算法
一般に、計算したい物理量\(Y\)が他の\(N\)個の物理量\(X_i(i=1,2,,,N)\)で計算されるとき。すなわち、\(Y=F(X_i)\)という状況を考える。この時、\(Y\)の不確かさ\(\sigma_{\bar{Y}}\)は、次のように計算される。
\[ \sigma_{\bar{Y}} = \sqrt{ \left( \frac{\partial F}{\partial X_1} \sigma_{\bar{X_1}} \right)^2 + \left( \frac{\partial F}{\partial X_2} \sigma_{\bar{X_2}} \right)^2 + \cdots + \left( \frac{\partial F}{\partial X_n} \sigma_{\bar{X_N}} \right)^2 } \]
先ほどの電流を計算する具体例に当てはめれば、\(Y=F(X_i)~\rightarrow I=F(Q,T)=Q/T\)であり\(N=2\)に対応する。したがって
\[ \sigma_{\bar{I}} = \sqrt{ \left( \frac{\partial F}{\partial Q} \sigma_{\bar{Q}} \right)^2 + \left( \frac{\partial F}{\partial T} \sigma_{\bar{T}} \right)^2 } \]ここで、
\[\frac{\partial F}{\partial Q}=\frac{1}{T}~,\quad\frac{\partial F}{\partial T}=-\frac{Q}{T^2}\]であるから、
\[\sigma_{\bar{I}} ~\simeq~ 8.329927~~~\mathrm{C/s}\]と求まる。有効数字は、今までと同様。
3.エクセルの活用
実際に計算するととても時間がかかりめんどうなことがわかる。エクセルを使うと簡単に計算できるのでその一例を紹介しよう。
3.1不確かさの出し方
次のコードを打てば計算できる。
平均 \[ =\mathrm{AVERAGE}(\text{データを範囲選択}) \]
不確かさ \[ =\mathrm{STDEV}(\text{データを範囲選択})/\mathrm{SQRT}(\mathrm{COUNT}(\text{データを範囲選択})) \]
これだけ、一度ほんとに合っているか確認してみると理解が深まるかもしれない。