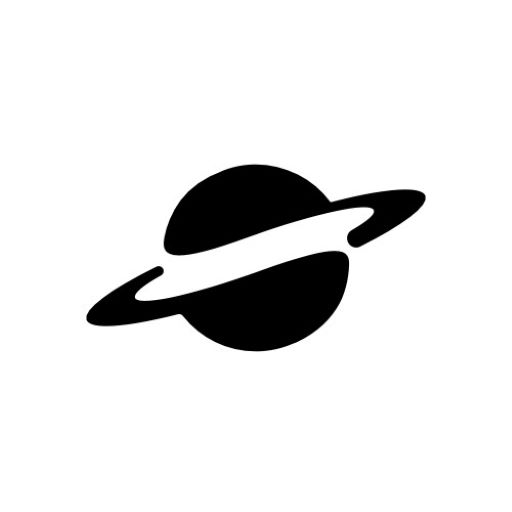1. はじめに
\(n\)元連立方程式の解の数は、係数行列のランクと未知数の個数によって決まります。この記事では、なぜ解が一意に決まる場合、無数に存在する場合、解が存在しない場合があるのかを詳しく解説します。
2. 連立方程式の基本形
\(n\)元連立方程式は以下の形で表されます
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$
これは行列形式で
$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
と表せます。ここで、\(A\)は\(m \times n\)係数行列、\(\boldsymbol{x}\)は未知数ベクトル、\(\boldsymbol{b}\)は定数ベクトルです。
3. 解の存在と一意性の判定
連立方程式の解の性質は、拡大係数行列のランクによって判定できます。
3.1 拡大係数行列
拡大係数行列は
$$[A|\boldsymbol{b}] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & | & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & | & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & | & b_m \end{pmatrix}$$
と定義されます。
3.2 解の分類
\(\text{rank}(A)\)を係数行列のランク、\(\text{rank}([A|\boldsymbol{b}])\)を拡大係数行列のランクとすると
- 解なし \(\text{rank}(A) < \text{rank}([A|\boldsymbol{b}])\)
- 一意解 \(\text{rank}(A) = \text{rank}([A|\boldsymbol{b}]) = n\)
- 解が無数 \(\text{rank}(A) = \text{rank}([A|\boldsymbol{b}]) < n\)
ランクの計算方法については、こちらで詳しく解説しています。
4. 具体例での理解
4.1 2元2式の場合
連立方程式
$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$$
の拡大係数行列は
$$[A|\boldsymbol{b}] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 5 \\ 2 & 4 & | & 10 \end{pmatrix}$$
- この行列のランクは \(\text{rank}(A) = 1\)(2行目は1行目の2倍)
- 拡大係数行列のランクは \(\text{rank}([A|\boldsymbol{b}]) = 1\)(2行目は1行目の2倍)
- すなわち、解が無数(自由変数1個)
4.2 解なしの場合
連立方程式
$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 11 \end{cases}$$
の拡大係数行列は
$$[A|\boldsymbol{b}] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 5 \\ 2 & 4 & | & 11 \end{pmatrix}$$
- この行列のランクは \(\text{rank}(A) = 1\)
- 拡大係数行列のランクは \(\text{rank}([A|\boldsymbol{b}]) = 2\)(2行目を1行目の2倍にできない)
- すなわち、解なし
4.3 一意解の場合
連立方程式
$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x – y = 1 \end{cases}$$
の拡大係数行列は
$$[A|\boldsymbol{b}] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 5 \\ 3 & -1 & | & 1 \end{pmatrix}$$
- この行列のランクは \(\text{rank}(A) = 2\)(2つの行は線形独立)
- 拡大係数行列のランクは \(\text{rank}([A|\boldsymbol{b}]) = 2\)
- すなわち、一意解 \(x = 1, y = 2\)
5. ガウスの消去法による判定
拡大係数行列を行簡約階段形に変形することで、解の性質を判定できます。
5.1 行簡約階段形
行簡約階段形では以下の特徴があります
- 主成分 各行の最初の非零成分が1
- 階段状 主成分は右にずれる
- 主成分列 主成分以外の成分は0
6. 斉次連立方程式
定数項がすべて0の斉次連立方程式
$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$$
について考えます。
6.1 斉次方程式の解
斉次方程式は常に自明解\(\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}\)を持ちます。
- 自明解のみ \(\text{rank}(A) = n\)のとき
- 解が無数 \(\text{rank}(A) < n\)のとき
6.2 解空間の次元
斉次方程式の解空間の次元は
$$\dim(\text{Ker}(A)) = n – \text{rank}(A)$$
で与えられます。ここで、\(\text{Ker}(A)\)は\(A\)の核(カーネル)です。
7. まとめ
\(n\)元連立方程式の解の数は以下のように判定できます
- 解なし \(\text{rank}(A) < \text{rank}([A|\boldsymbol{b}])\)
- 一意解 \(\text{rank}(A) = \text{rank}([A|\boldsymbol{b}]) = n\)
- 解が無数 \(\text{rank}(A) = \text{rank}([A|\boldsymbol{b}]) < n\)
この判定法により、連立方程式の解の性質を効率的に調べることができます。特に、ランクの概念が解の存在と一意性を決定する重要な役割を果たします。