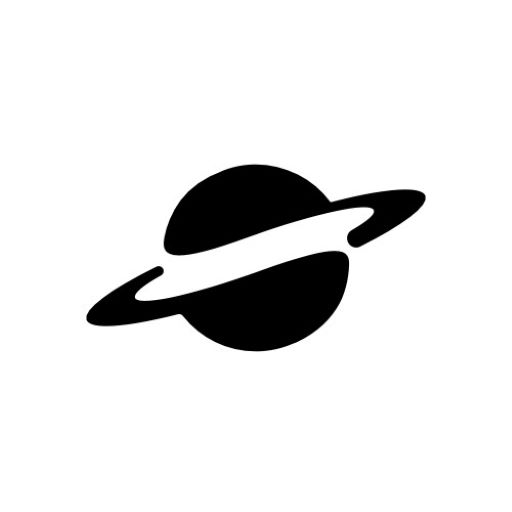1.近似直線
1.1近似直線(回帰直線)とは
物理現象が理論的に一次関数になる。このような状況で理論と実験を照らし合わせるための手法である。例えば、フックの法則がそれにあたる。
\[F=kx\]
実験で、力\(F\)とばねの伸び\(x\)を計測したとして、以下の結果が得られた場合を考える。
| 変位 \(x\) [m] | 力 \(F\) [N] |
|---|---|
| 0.00 | 0.03 |
| 0.10 | 0.30 |
| 0.20 | 0.59 |
| 0.30 | 0.94 |
| 0.40 | 1.17 |
| 0.50 | 1.50 |
| 0.60 | 1.85 |
| 0.70 | 2.08 |
| 0.80 | 2.41 |
| 0.90 | 2.68 |
| 1.00 | 3.02 |
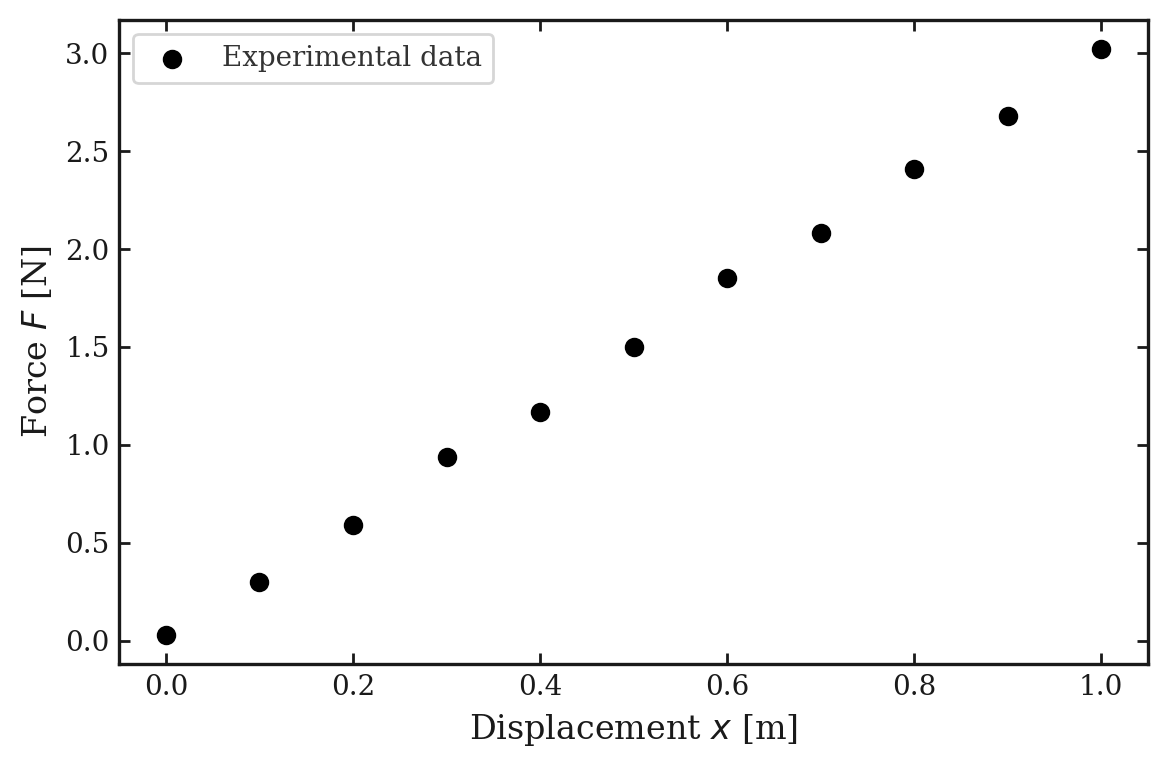
ここにふさわしい直線を計算することができ、今回の場合は
\[ F = (2.99 \pm 0.03)\,x + (0.011 \pm 0.015) \]
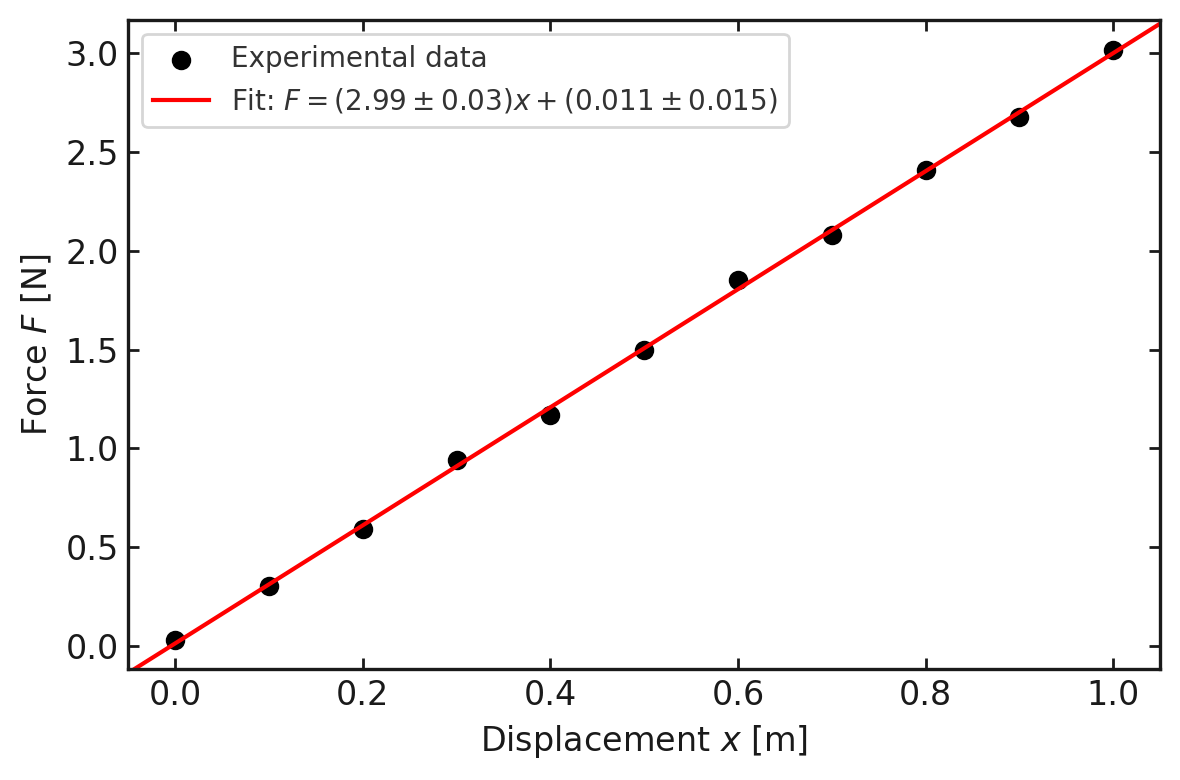
となる。次の章で具体的な計算方法を見る。
1.2近似直線の計算法(最小二乗法)
次のような状況を考える。
| \(Y\) [unit] | \(X\) [unit2] |
|---|---|
| y1 | x1 |
| y2 | x2 |
| ⋮ | ⋮ |
| yk | xk |
| ⋮ | ⋮ |
| yN | xN |
次を計算しておく。
\[S_X=\sum_{k=1}^{N}x_k,\quad S_Y=\sum_{k=1}^{N}y_k ,\quad S_{X^2}=\sum_{k=1}^{N}x_k^2 ,\quad S_{Y^2}=\sum_{k=1}^{N}y_k^2 ,\quad S_{XY}=\sum_{k=1}^{N}x_ky_k\]
このような実験結果が、どんな一次関数できるかは、次の式でもとまる。傾きと切片は
\[a=\frac{NS_{XY}-S_XS_Y}{NS_{X^2}-S_X^2},\quad b=\frac{S_{X^2}S_{Y}-S_XS_{XY}}{NS_{X^2}-S_X^2}\]
で計算できる。しかし、これではこのデータの信用度がわからない。不確かさを計算する必要がある。\(S_X^2\neq S_{X^2}\)に注意。
1.3近似直線の不確かさ
不確かさは、次の式で求められる。実際に具体例で計算すると身につくかもしれない。
\[\sigma_{\bar{a}}=\sigma_{\bar{Y}}\sqrt{\frac{N}{NS_{X^2}-S_X^2}},\quad \sigma_{\bar{b}}=\sigma_{\bar{Y}}\sqrt{\frac{S_{X^2}}{NS_{X^2}-S_X^2}}\] \[\text{ただし}~~~\sigma_{\bar{Y}}=\sqrt{\frac{1}{N-2}\sum_{k=1}^{N}\left(y_k-ax_k-b \right)^2 }\]
まとめて、次のように表記する。有効数字は、不確かさの慣例に従う。
\[Y=\left(a\pm \sigma_{\bar{a}}\right)X+\left(b\pm \sigma_{\bar{b}}\right) \]
2.エクセルの活用
実際に計算するととても時間がかかりめんどうなことがわかる。エクセルを使うと簡単に計算できるのでその一例を紹介しよう。
2.1近似直線の出し方
- 手順1: エクセルに数値を二列に並べる。
- 手順2: 傾きと切片の結果を出したいところに
=LINEST(Yのデータを選択, Xのデータを選択)
を入力すると、左に傾き、右に切片が出力される。 - 手順3: 傾きと切片の不確かさを出したいところに
=INDEX(LINEST(Yのデータを選択, Xのデータを選択, TRUE, TRUE), 2)
を入力すると、左に傾き、右に切片の不確かさが出力される。
一度自分で計算したものと比べて見ると、理解が深まるかもしれない。